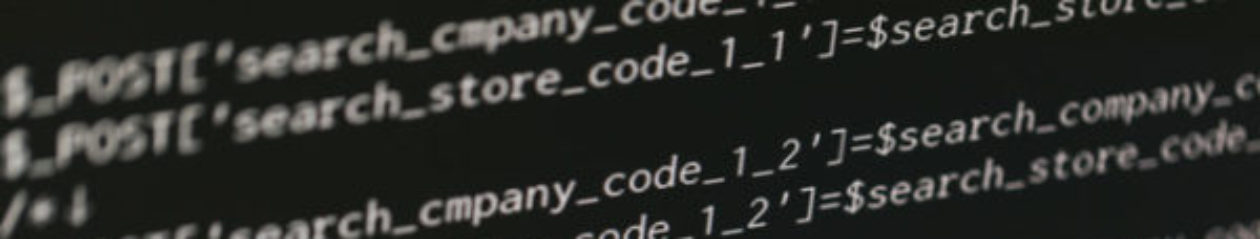寒い冬のとある前日のこと。夕食がすんで家族そろってテレビを
視聴していた時、小学2年生の末っ子のぼうずが
「かあちゃん、あした、知っとる? 」母親はテレビを見ながら
みかんをひとふさむいては口にほうばっている。
(ここ愛媛は全国きっての言わずと知れた有数のみかん
産地だ) なおもぼうずが「知っとる? 」
「ねえっ、知っとる? かあちゃん」母親はうっとしそうに、
聞こえないふりをしているのか、聞いていないのか、なおも今も
みかんに手を伸ばし、くちゃくちゃと口を動かし、
子供の話をさえぎるように
「**ちゃん、あんたも食べんかい、」「おいしいよ」と、
かたわらのダンボール箱(当時、生産過多から知り合いの農家
から闇で超格安(市場の半値以下)で手に入れていたのだ)から
さらに2個取り出しその一個を愛息子に差し出した。
受け取った少年はみかんをこたつの
上に置き、「かあちゃん、 知っとる」
「クリスマス、って知っとる」「あした、クリスマス」
(母)「え、え」(子)「クリスマスー」
(母)「え、クリスマスー」
(子)「そう、クリスマス、聞いたことある? 」
(母)「うん、聞いたことあるよ、クリスマスやろ」
ようやく、みかんから手を離し、耳を傾けようと
母親は子供に目を向けた。機嫌が悪ければ、いちもにもなく、
はねつけられるところではあるが、食欲が満たされていたのか。
それから後、親子は互いに言い合った、末っ子のおねだりを
母親はしぶしぶ、一部認めた。
「ケーキ、作ってあげるよ」
「ほんと」「ケーキなんか作れるん?」
「作っていらんけん、買うて、買うて」
「買うたら高いんやし、作ったほうが美味しんよ」
「ケーキくらい、かあちゃんでも作れるんよ」
「ほんとかいな・・・・」
「めちゃめちゃ美味しいの作ってあげるよ。」
自信ありげな母親の言葉に同意せざる得ない少年は
何か不安ながらも、初めて見るであろう母親手作りの
ケーキにいくぶん期待を寄せていた。
現代のように欲するものがわずかなお金で手軽に手に入る
時代とは違う《当時》・・ 食べることが何よりも《しあわせ》
そんな時代、ハイカラでシャレた《ケーキ》なんて裕福な友人の
家でごしょうばんにあずかることでしか口にできない
あこがれのお菓子を、
あの昭和ひとけたの、いなかの土のにおいしかしない、
あの《どけち子》の女性が・・・ ほんとにできるんかな?
《どけち》と料理のうまいへたは何の関係もないところだが・・
当日の夕刻、日がすでに暮れかかっている。いつもの食事時間
まで、もういくばくもない。しかも、それらしいブツは今もって
一ミリも目にできない。待ちきれない小僧がおそるおそる
問うた。
「ケーキ、いつできるん? 」「もうすぐ」
「いま、作ってる? 」「まだ・・・」
「もう時間ないよ、みんな帰って来るよ」
「ごはんのおかずが先やろ」子供が居間でテレビを見ながら
母親に問いかけながらせっつく。母親は我関せず、土間で
ドタバタと食事の準備にてんやわんやで大わらわ。
しばらくして、土間の東となりの風呂場の火入りを祖母が
いつものルーティーンでおこなったのか、すりガラスの
戸のすきまからあかあかと暖かな明かりがもれていた。それが
発端に家族がぞろぞろと集まり始めた。姉、兄がテレビの
チャンネル争いで騒がしい、兄が力ずくでテレビの画面の
前いっぱいにしゃがみこみなめるように見ている。
「**ちゃん、 そんな近くで見たら、目悪なるよ」
母のこごとが耳ざわりだが、兄には効いたのかテレビから
距離をとった。「****」「ごはんできたけん」
「テーブル出して、ふかんかね」と、姉に手伝うように
少しきつく催促する。姉はうつぶつ何やら言いながら
むっつりとした表情でいやいや従う。
「***も手伝って」「お皿出して」
「うん」仕方なく、ぼうずも手伝う。「**ちゃん」
「皿こっちへ持ってきて」母の言葉に命じられるまま
鍋から皿へおかずをよそおい渡されると文句を言う。
「また、さかな・・・他には ?」「ない」と、ぴしゃり。
「ケーキは? 」「ごはんのあとで作る」
「デザートは最後やろ」 (奇妙なことに、なぜだか、
こんなところは知っているのが、不思議な母なのだ。)
9人もの家族が丸いテーブルを囲んで座ると白米をちゃわんに
いつものように祖母がすくい各自に手渡す、その間、次男と自分
のために酒を温めている。(おじと祖母の何よりのたのしみ)
小さなおかずひとすくいに対して大きな白米2、3口とは貧乏人
の常識であろう。お腹が満たされつつあるころ、土間のわきでは
ぐつぐつと大きなやかんが音を立ててにたっている。それを
合図に母がようやく、ケーキ作りの準備に取りかかったようだ。
姉と祖母も手伝いに加わった。祖母が洗った皿を丁寧にふきんで
拭いている。母がひろげた材料の包み紙を両手でまるめて土間に
隠し捨てた。その後、母と姉が白いクリームをマーガリン用
のコテで薄く伸ばしているようだ。ゴソゴソしているとじきに
何だかできあがったようで、皿に盛りつけていた。
「何飲む? 」「コーヒー」「お茶」生まれて初めてコーヒーを
作ってもらうと祖母が眉間にしわを寄せて
「子供に、コーヒーなんか飲ませられん」と母にきつくどなる。
むっとした表情で一瞬祖母をにらんだが、言葉をのみ込んだ
ようでいらいらしていた。(とついで以来、母と祖母は
よくいがみあっていたようだが、父は知らんぷりを決め込んで
いたようで、母はいつもひとり陰で泣いていたそうだ)
そんなことはつゆも知らない子供たちは、おのおの身勝手に、
振る舞っていたため、ここでも、子供たちは熱くて
飲みかねるコーヒーをスプーンですくって
ちょびちょび飲んでいた。
待ちに待った・・・いよいよ、やっとこさ実食だ。
兄とぼうずはひと目見てこうべをたれ、言葉を失った。
母の主張する《ケーキ》のその実態とは、
母の好物の「ミルクブレッド」という市販のパンで、
薄くて小さい子供の手のひらサイズの食パンに
白クリームが両面に塗られて、横に横にと重ねられた
だけの味付けパンで、安価でボリュームのある、
お買い得のパンなのだ、
そのパンを半分ほど5センチほど上に重ねて皿にのせて、
一番上のパンの上に、
なんとこともあろうことか、
マヨネーズで、小さく遠慮ぎみに、
《ケーキ》とかかれたものなのだ。(ただ、《ケーキ》とかき
こんだだけでまさに名札を付けたごとくの、
自称する《ケーキ》だけのものなのだ)味はともかく。
その横には、ご愛嬌にありふれたみかんの
ひとふさがふたつほど
大きな顔してちんざしているではないか。
でも最悪のことに、マヨネーズのちょっぴりの塩気で、
クリームの甘さが台無しで、
とんと食べられたもんじゃなかった。
兄とぼうずは土間にまるめて捨てられた
見慣れた袋包みを見逃さなかった。
ふたりは顔を見合わせて軽くうなずくだけであった。
ぼうずは母親を見た。
母は、「おいしかろ? 」とぬけぬけとほざきやがった。
返事するのもアホくさく、黙ってとにかく口に押し込んだ。
母親はさもありなんのごとく、ごくごく普通の面持ちで
コテや皿に残ったクリームを
誰気がねなく集めてなめて、(ほんにずぶとい)
コーヒーで流し込んでいた。
《けちくさい》にも程があるもんだと、ぼうずは
行き場のない《いきどおり》をいつものように
腹の中に押し込み、くちびるをかみしめ、涙をこらえ
自分の貧しい身の上をあらためて思い知らされたのだった。
でも、こんな母親でもなぜだか決して憎めない
嫌いになれない、本音で笑って見つめられる顔が
忘れられないのだ、
妙にいとおしいのだ。これが血縁というものか ?
今日はここまで。近藤浩二でした。
ではまた。また逢う日まで。
両親のこの手の《子供だまし》には度肝を抜かれたもんだ。
母が夕食に《お子様ランチ》を作ると豪語したのだが、
父が夕食前に、長いつまようじに紙をまきつけ、日の丸の旗を
描き、ワンプレートで、おちゃわん型の白米に刺し付けただけ
だったのだが。これは当時、子供だましで広まった《手》
だったとうわさでよく耳にした。
今この話を母にしても、素知らぬ顔で、
「そんなことあった? 」とちっとも取り合ってくれない。
けたはずれのずぶとさは、今もって健在だ。
そんなハハのおかげなのか、いまだに、
なんでもおいしくたべられる、しあわせものだ。